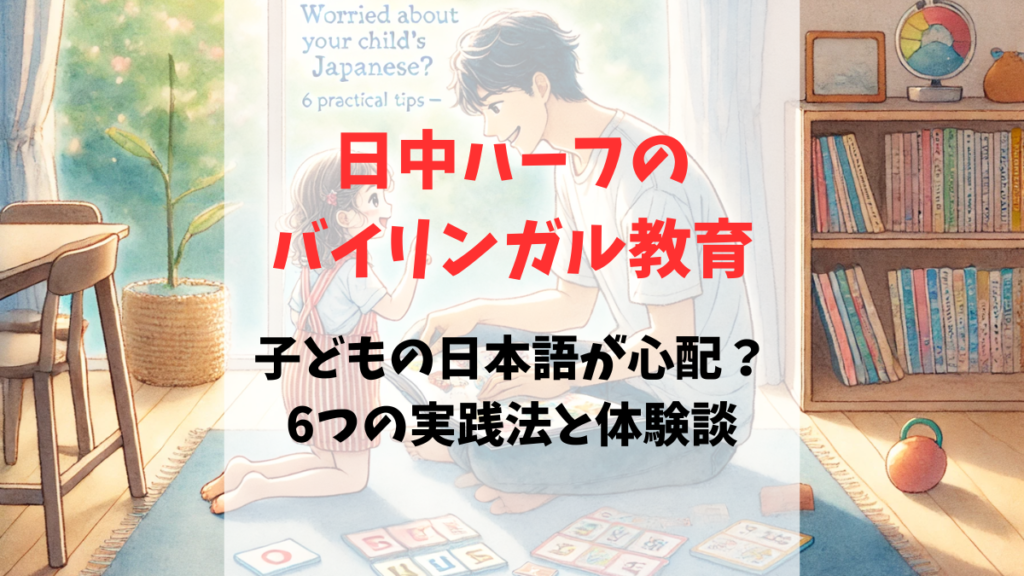
日中ハーフの子どもを育てる親なら、誰もが一度は考えることではないでしょうか?
でも、実際にバイリンガル教育をやってみると…
✓どちらかの言語が弱くなる
✓混ぜて話す(ちゃんぽん)問題
✓子どもが言語習得を嫌がる
など、さまざまな課題が出てきます。
この記事では、筆者が中国で実際に子どもをバイリンガルに育てるためにやってきた方法を紹介します。
この記事はこんな人におすすめ
- 海外在住で子どもの日本語力が心配な方
- バイリンガル教育の実践方法を知りたい方
- 本帰国後の子どもの適応が不安な方
我が家の環境とバイリンガルの課題

私自身、中国の上海人の奥さんと2005年に籍を入れ、長女と長男を授かり、子供が高校にあがるまで、現地の幼稚園、小学校、中学校に通わせていました。
👉筆者プロフィールはこちら
我が家は、子どもが現地での生活に馴染み、将来の選択肢を広げられるよう、中国の現地校を選びました。
さらに、平日は義父母が子どもを見てくれていたため、家庭内でも自然と中国語中心になりがちでした。
そこで、夜や週末はできるだけ日本語で話し、インプットの機会を増やすことを意識しました。
バイリンガル教育は、各家庭の環境や子どもの性格によって方法が異なります。
これが唯一の正解というわけではありませんが、私と似た環境や境遇の方には参考になるかもしれません。
では実際に、我が家で実践してきた方法を紹介します。
我が家で実践したバイリンガル教育の方法

ここからは我が家が実践していたバイリンガル教育の方法を紹介します。
我が家で実践したバイリンガル教育の方法
- 日本の通信教育を活用(こどもチャレンジ)
- 夜寝る前に日本語の絵本を読む
- 言い間違いを訂正せず、自然に言い直す
- 日本のアニメ・漫画を一緒に見る
- 日本語補習校に通う
- 長期休みは日本の学校へ編入する
一つずつ詳しく解説していきます。
1. 日本の通信教育を活用(こどもチャレンジ)

楽しみながら勉強していました
我が家では、日本語教育のために「こどもチャレンジ」を日本の実家から定期的に送ってもらいました。
月1回届く教材を3カ月分まとめて送ってもらい、週末に子どもと一緒に取り組むことで、自然と日本語に触れる機会を作りました。
教材にはDVDや絵本、ワークブックが含まれており、遊びながら学べる内容になっています。
特に「見る・聞く・話す」の要素が含まれているのがポイントで、子どもも楽しみながら続けることができました。
効果があったポイント
✅ DVDを一緒に見て、歌を歌う → 日本語のリズムや発音に慣れる
✅ 絵本やワークで、楽しみながら日本語を学ぶ
✅ 決して「勉強」にならないよう、遊び感覚で続ける
もっとくわしく!
-

-
海外で「こどもちゃれんじ」|国際結婚家庭バイリンガル育児体験談
続きを見る
2. 夜寝る前に日本語の絵本を読む

日本帰国の度に本を買って帰ってました。
我が家では、「日本語の読み聞かせ」を習慣化するために、毎晩寝る前に絵本を読むようにしました。
こどもチャレンジにはオリジナルの絵本がついていたので、それを活用しながら、日本語のインプットの機会を増やしました。
また、日本に一時帰国した際には、子供へのお土産は日本の絵本や子ども向け雑誌でした。
特に、付録付きの雑誌は一緒に遊ぶことでスキンシップの時間にもなり、自然と日本語を使う機会が増えました。
絵本の効果
✅ 言葉だけでなく、日本文化や昔話にも親しめる
✅ 「日本人なら誰でも知っている話」を共有できる
✅ 「これ、パパに読んでもらったよね?」と話題がつながる
ただ、頻繁に日本へ帰れない方や、日本から遠方に住んでいる方にとっては、日本の絵本を手に入れるのは難しいですよね。
今は、電子絵本を活用すれば、日本にいなくても日本語の絵本を読むことができます。
3. 言い間違いを訂正せず、自然に言い直す

遊びの中で自然に日本語を使うきっかけに
我が家では、子どもが言葉を間違えたとき、直接訂正せずに自然な会話の中で覚えさせることを意識しました。
バイリンガルの子どもは、日本語と中国語を混ぜて話してしまうことがよくあります。
例えば、うちの子はこんな風に話していました。
👧 「パパ、啤酒飲んでるの?」(ビール → 啤酒)
この時、「違うよ、ビールって言うんだよ!」と訂正するのではなく、
🧑 「そうだよ、パパはビール飲んでるよ。」と自然に言い直しました。
こうすることで、子どもは「正しい言葉」を無意識のうちに吸収するようになります。
ポイント
✅ 訂正すると「間違えた!」と感じてしまい、日本語を話すのが嫌になることも
✅ 自然な会話の中で正しい表現を覚えられるようにする
4. 日本のアニメ・漫画を一緒に見る

ゲームもよくやりました
我が家では、日本語に触れる「楽しい時間」を作るために、子どもと一緒に日本のアニメや漫画を楽しむことを意識しました。
日本のアニメや漫画は、バイリンガル教育にとても効果的なツールですが、ただ見せるだけでなく、親も一緒に見ることが大事!
効果的な見方
✅ 一緒に見ることで、共通の話題が生まれる
✅ アニメのセリフを真似して遊ぶと、会話の機会が増える
✅ 親が日本語でリアクションを取ると、子どもも自然と日本語を話すようになる
特に、子どもが好きなアニメを通じて、日本語を使う機会を増やすのがポイントです。
子どもと同じ目線で楽しめるので、親子の会話も自然と増えていきます。
5. 日本語補習校に通う

上海補習クラブの様子
我が家の住んでいた上海には日本語補習校があり、小学校から通っていました。
※正式名称は「上海日本語補習クラブ」。公式ページはこちら。
日本語補習校とは?
子どもの日本語教育をサポートするために、親のボランティアによって運営されている学校で、日本人が多く住む都市には設立されていることが多いです。
上海の補習クラブでは、入学式や運動会、社会科見学、卒業式など、日本の学校と同じようなイベントがあり、まるで日本の学校に通っているような感覚で過ごせました。
また、中国の学校では親や教師が何でもやってしまう環境ですが、補習クラブでは子どもが自分で考え、行動する機会が多かったのが印象的でした。
- 発表会の内容を自分たちで企画
- 運動会の練習を自主的に進める
- 卒業文集を作成する
こうした経験を通じて、日本語だけでなく、自主性や協調性も育まれる貴重な機会になったと感じています。
日本語補習校のポイント
✅ 日本の学校と同じような環境で学べる
✅ 日本語の読み書きを定期的に学習できる
✅ イベントを通じて、日本文化に触れられる
✅ 自主性を育む機会にもなる
👉世界各国の補習校の一覧は、外務省公式の最新リストから確認できます。
お住まいの都市に補習校がない場合でも、今は、日本にいなくても子ども向けのオンライン講座で日本語学習をサポートできるサービスが増えています。
おすすめは「eFFISAGE!(エフィサージュ)」
自宅で日本の学習をオンラインで受けられ、帰国後の受験対策や学力維持にも最適です。
あわせて読みたい
-

-
海外子女の国語・受験対策に|eFFISAGE(エフィサージュ)が選ばれる理由と評判
続きを見る
6. 長期休みは日本の学校へ編入する

私の母校に子供たちが体験入学
我が家では、夏休みや冬休みなどの長期休みに、日本の学校へ一時編入することで、日本語の学習を継続していました。
短期間でも日本の授業を体験することで、日本語の読み書きや学校のルールに慣れる貴重な機会になりました。
日本の学校に一時編入するメリット
✅ 日本の授業スタイルや学習環境に触れられる
✅ 読み書きの実践機会が増える
✅ 日本の同年代の子どもと交流できる
✅ 将来的な帰国に向けた適応力を養える
ただし、編入や体験入学の受け入れは、国の制度として全国一律に定められているわけではなく、各自治体(教育委員会)が裁量で判断しています。
文部科学省のFAQ(海外からの一時帰国に関する案内)にも、「体験入学は全国共通の制度ではなく、各教育委員会が対応を決めている」と明記されています。
その場合は、子どもだけで参加できるツアーに申し込むのもおすすめです。
我が家も、長女が高学年になると編入を嫌がるようになったため、ツアーに参加させたところ、修学旅行のような良い思い出になりました。
バイリンガル教育の結果と現在の我が家

ヘルシンキ・アイスランドに留学した娘
我が家は、中国・上海で現地校に通うバイリンガル教育を実践してきましたが、2023年に日本へ本帰国しました。
当時、長女は高1、長男は中3。子どもたちにとっては日本で暮らすのが初めてで、日本語の授業についていけるのか不安もありました。
ただ、会話レベルは問題なく、半年もかからず日本の授業にも適応できました。
一方で、中国語を忘れないように、妻との会話は中国語を続け、中国の友達とはSNSでつながるようにしています。
特に、日本では中国語を使う機会が限られるため、「話す環境」を家庭内で維持することが重要だと感じています。
また、中国時代は宿題が多く、深夜まで勉強する日々でしたが、その経験もあってか、英語の成績はクラスでも上位。
長女は早速、夏休みや春休みを利用してイギリスや北欧に短期留学するようになりました。
もちろん大変なこともありましたが、家族で工夫しながら学ぶ環境を作ってきたことが、今につながっているのだと思います。
まとめ|なによりも家族の時間が大事!
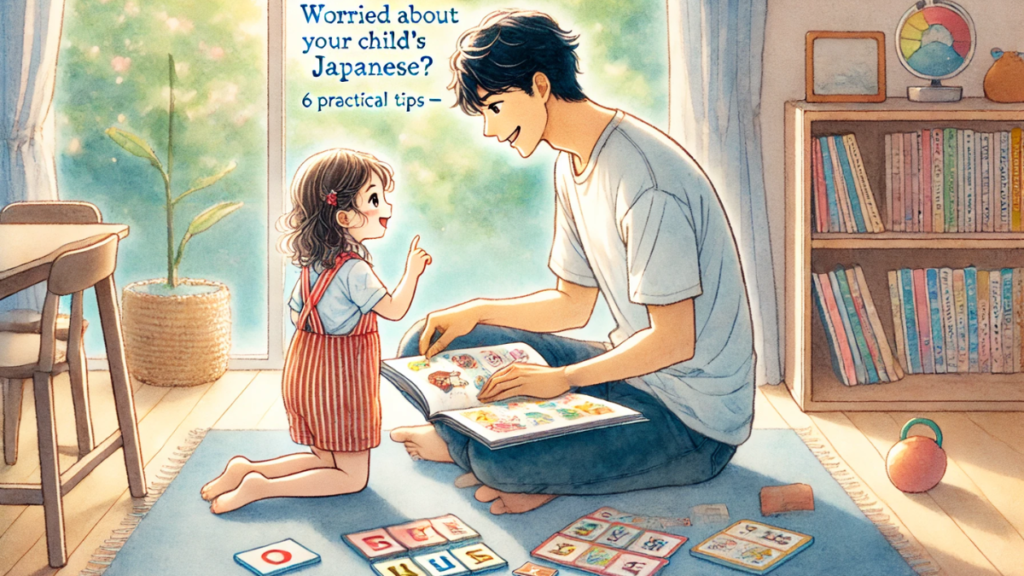
いかがでしたか?
私の体験を通して、バイリンガル教育のリアルな実践例を共有させてもらいました。
この記事で紹介した内容を振り返ると、我が家では以下のような方法を実践してきました。
我が家で実践したバイリンガル教育の方法
- 日本の通信教育を活用(こどもチャレンジ)
- 夜寝る前に日本語の絵本を読む
- 言い間違いを訂正せず、自然に言い直す
- 日本のアニメ・漫画を一緒に見る
- 日本語補習校に通う
- 長期休みは日本の学校へ編入する
バイリンガル教育に「絶対の正解」はありません。
家庭の環境や住んでいる場所、子どもの性格によって、最適な方法は変わります。
ただ、私がひとつ確信しているのは、「家族の時間」が何より大切だということ。
どんな方法を選ぶにせよ、子どもと一緒に過ごす時間を大切にすることで、自然と学び続ける環境を作ることができると実感しています。
バイリンガル教育は、ただの「勉強」ではなく、「家族の関わり」そのもの。
この記事が、少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです。

