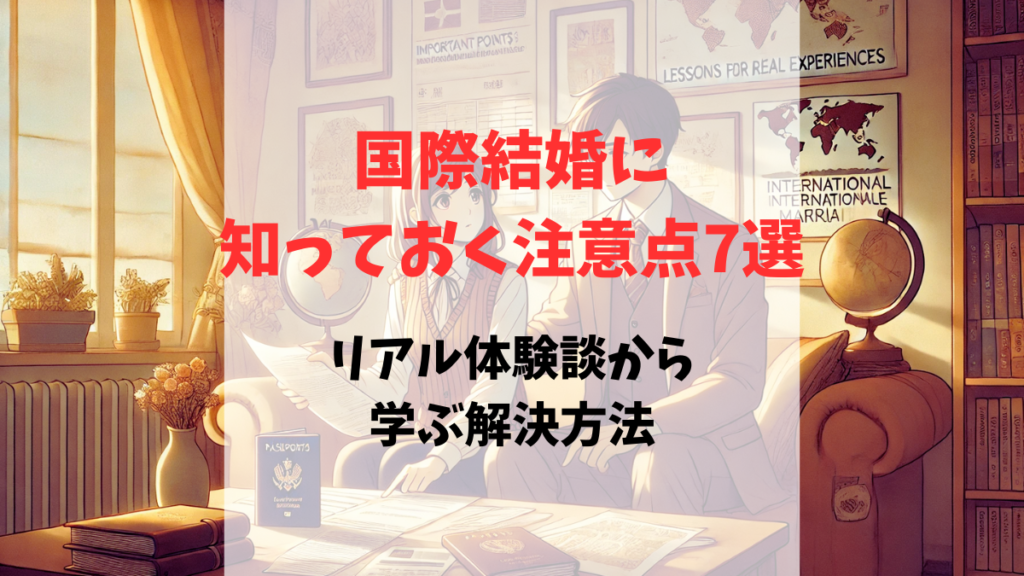
恋人が外国人で、結婚を視野に入れ始めたとき、多くの人がこうした疑問を持ちます。
言葉や文化の違いを乗り越えられるのか、家族はうまくやっていけるのか、結婚後の生活にどんなことが待っているのか──。
実は、「好き」だけでは乗り越えられない壁もあるのが国際結婚。
恋人との関係がうまくいっている今こそ、将来起こり得るすれ違いやトラブルについて知っておくことで、結婚後のギャップを減らし、より良いパートナーシップを築くことができます。
この記事では、筆者自身の経験を交えながら、結婚前にぜひ話し合っておきたい7つのポイントとその解決策をご紹介します。
1. 文化や生活習慣の違い

国際結婚では、食文化や生活習慣の違いが日常のストレスにつながることがあります。
たとえば、休日の過ごし方や「毎日の献立」ひとつをとっても、話し合いが必要になることがあります。
我が家の場合は、春節(旧正月)と日本の夏休みをどう過ごすかが大きなテーマでした。
どうしたらうまくいく?我が家の解決策
- 「どちらが正しいか」ではなく「両方をどう大切にできるか」を話し合う
- 「自分の当たり前は相手には違う」と理解し、譲れる部分と譲れない部分を整理する
こうした工夫を取り入れることで、どちらか一方を我慢させるのではなく、両方の文化を尊重できるようになりました。
こうして年間のバランスをとることで、どちらの文化も自然に取り入れられました。
2. ビザや婚姻手続きの煩雑さ
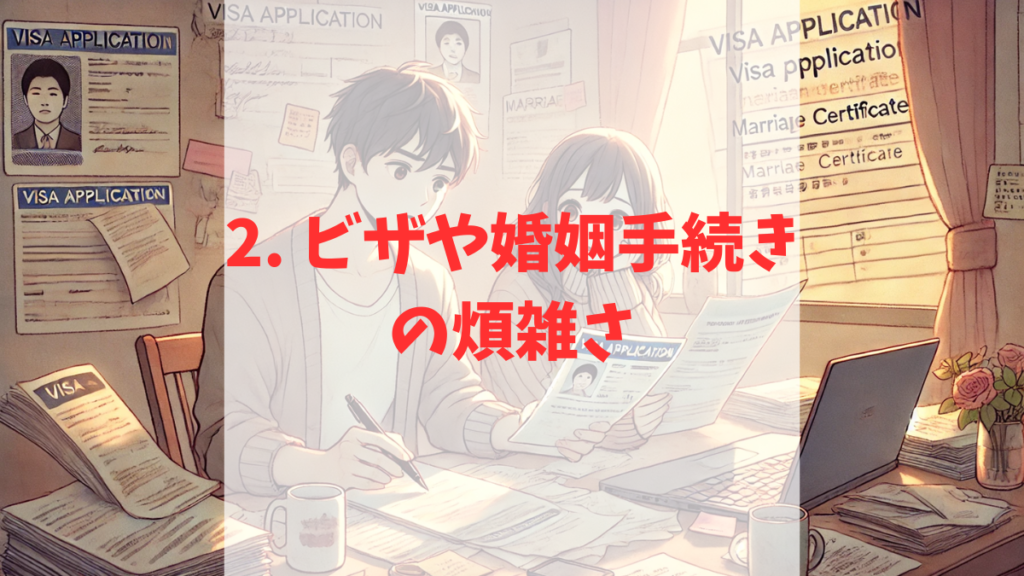
国際結婚では、ビザの取得や婚姻の手続きなど、国内結婚にはない“書類の壁”に直面します。
必要な書類は国によって異なり、翻訳・認証・申請の順序も複雑。
知らずに進めると、思わぬタイムロスやトラブルにつながることもあります。
どうしたらうまくいく?我が家の解決策
- 手続きは感情ではどうにもならない“制度との戦い”と心得る
- 事前に流れを調べ、必要なら行政書士や弁護士に早めに相談する
- スケジュールや必要書類を二人で共有し、相手任せにせず協力する
思わぬ外部要因で、予定がずれ込むことがあります。
「どの書類でどのくらいかかるか」を逆算して同時並行で進めるのがおすすめ。
例えばこんな体験談…
-

-
国際結婚で必要な在留資格の流れ|在留カード取得までの手続きと体験談
続きを見る
3. お金に関する価値観の違い
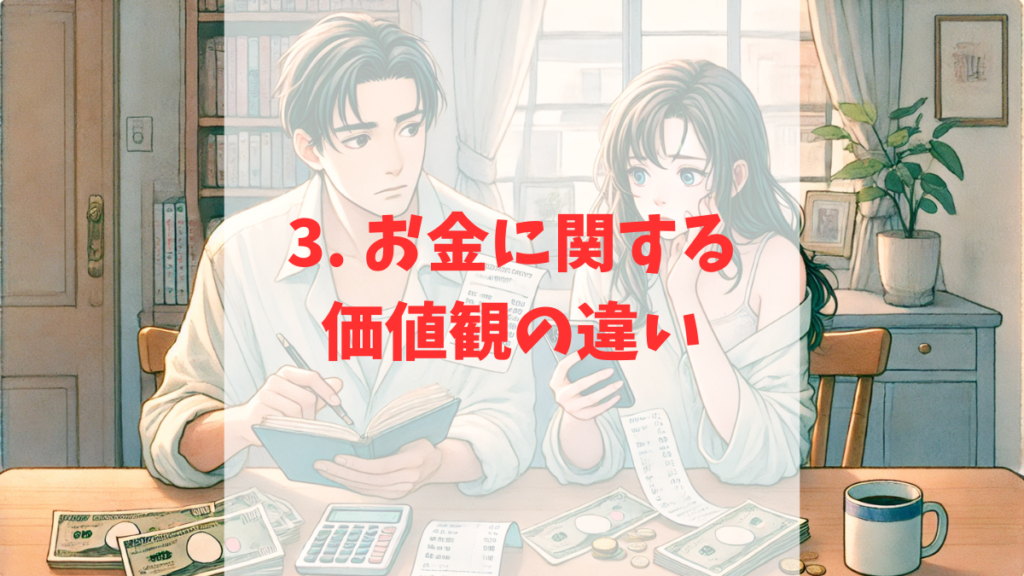
国際結婚では、「お金の使い方」に対する考え方の違いが、予想以上にストレスになることがあります。
たとえば、中国や東南アジアでは「家族への仕送りや支援が当たり前」とされる文化があり、そこから双方の認識に大きなズレが生じやすくなります。
実際に、筆者の中国人の妻も、実家だけでなく親戚にも高価な贈り物を送ることがあり、「そこまでするものなの?」と驚いたことを覚えています。
どうしたらうまくいく?我が家の解決策
- 「どちらが正しいか」ではなく互いの文化や価値観を前提に理解する
- 家計を「生活費」「貯蓄」「支援」と明確に分けて管理する
- 家族への支援は予算化して計画的に行う
筆者自身も、家族の将来を考えて転職エージェントに登録したり、副業の可能性を探ったりしてきました。
同じように、将来の安心のために今から少しずつ準備を始めてみることをおすすめします。
国際結婚におすすめ副業
-

-
国際結婚だからこそできる副業6選|夫婦で収入を生み出すリアルな方法
続きを見る
4. 子育ての方針の違い
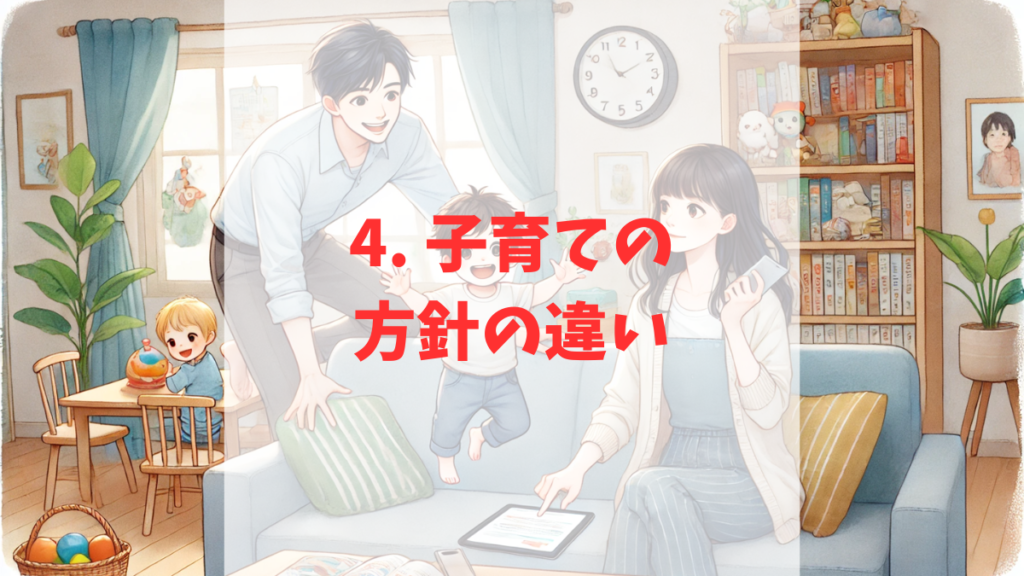
国際結婚では、子どもが生まれてから初めて「価値観の違い」に直面する夫婦も少なくありません。
たとえば、「日本語と相手の言語、どちらを優先するか」「厳しく育てるか、のびのび育てるか」「どの国の学校に通わせるか」など、教育方針ひとつとっても意見が分かれることがあります。
筆者の家庭では、「子どもにどの言語を第一言語として教えるか」が大きなテーマになりました。
日本語を話せなければ私の親と会話ができないし、中国語が弱ければ妻の家族と疎遠になってしまう──そんな不安が両方にあったのです。
どうしたらうまくいく?我が家の解決策
- 「何語で育てるか」だけでなく子どもが育つ環境全体を夫婦で考える
- 学校と家庭で役割を分担し、両方の言語に自然に触れられるようにする
- 文化の違いも「体験」として取り入れ、アイデンティティを尊重する
海外在住の場合は、夏休みを利用して日本の小学校への体験入学や、子どもだけのツアーに参加するのもおすすめ。
こうした経験を通して、日本語や文化に自然に触れる時間は、子どもにとって貴重な財産になります。
あわせて読みたい
-

-
子どもの日本語が心配?日中ハーフのバイリンガル教育|6つの実践法と体験談
続きを見る
5. 家族・親戚との関わり方
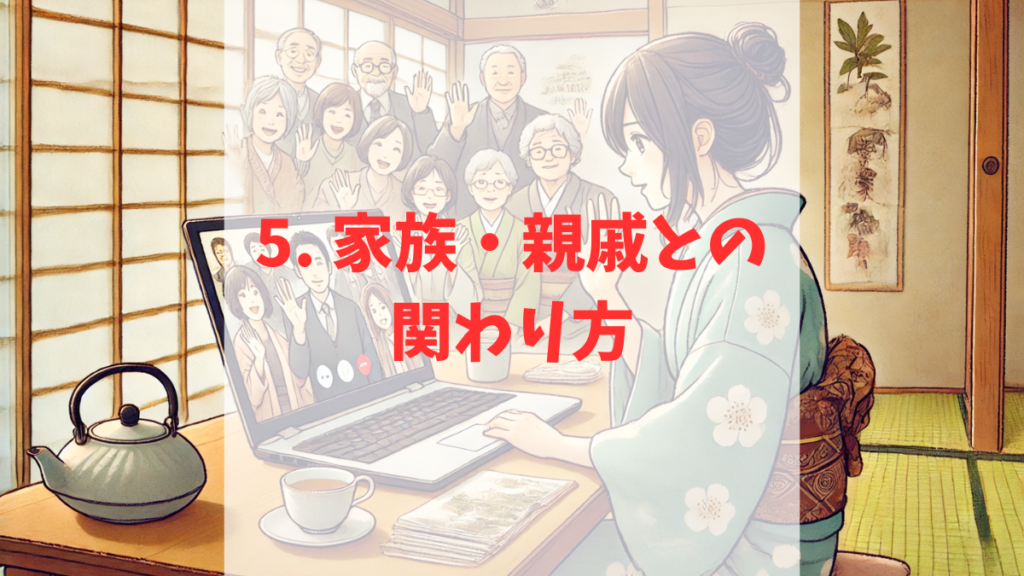
国際結婚では、親や親戚との距離感に関する「常識」が国によってまったく異なります。
たとえば、日本では「事前に連絡する・気を遣う」が当たり前でも、相手の文化では「気軽に訪ねる=愛情表現」とされることもあります。
筆者の家庭でも、妻の母からのビデオ通話が頻繁に来たときは最初こそ戸惑いましたが、妻にとってはそれが「普通」の感覚でした。
ただ、その家族のつながりの強さがあったからこそ、ちょっとしたことも気軽に相談でき、育児や生活の面で精神的に支えられてきたと感じています。
どうしたらうまくいく?我が家の解決策
- 「家族・親戚との距離感は国によって違う」と前提をパートナーと共有する
- 「ビデオ通話は週末だけ」「事前連絡なしの訪問は断る」など無理のないルールを決める
- 違和感があるときは直接ではなく、パートナーを通して伝える
親や親戚との関わりで違和感を覚えたときは、パートナーを通じて調整することが、関係をこじらせないコツです。
6. 住む国の選択

「日本で暮らしたい」「相手の国で家族のそばに住みたい」──
国際結婚では、住む国の選択が大きなテーマになります。
仕事、子育て、教育、親の介護…。
お互いの人生に関わる問題だからこそ、どちらか一方の希望だけで決めることはできません。
どうしたらうまくいく?我が家の解決策
- 「どこに住むか」ではなく「なぜそこに住みたいのか」を夫婦で共有する
- 感情ではなく、仕事・子どもの進学・親の介護など現実的な視点から考える
- 一度で決めず、家族の状況に応じて柔軟に移動する選択肢も持つ
子どもの高校進学をきっかけでしたが、その後も妻が中国へ帰国しやすいように、空港に近い場所を選ぶなど工夫しました。
完璧な答えはありませんが、夫婦で将来のイメージをすり合わせておくことが一番大切です。
7. 国際結婚後の孤独感・アイデンティティの揺らぎ

国際結婚では、慣れない国で暮らすことで孤独感やアイデンティティの揺らぎを感じることがあります。
言葉がうまく通じない、人間関係が築きづらい、文化や価値観が違う──
こうした積み重ねが「自分の居場所がない」と感じさせてしまうことも少なくありません。
私自身も中国で暮らし始めた頃、職場で気軽に話せる相手がいない時期があり、孤独を強く感じました。
どうしたらうまくいく?我が家の解決策
- 言葉が通じる仲間や安心できるコミュニティを持つ
- 日本人会・国際交流イベント・語学学校・SNSグループなどを活用
- 将来は自分が支える側になるかもしれないと意識し、相手の気持ちに寄り添う姿勢を持つ
逆の立場で、パートナーが日本で暮らしている場合も同じです。
孤独感や疎外感を感じやすいからこそ、しっかりケアして寄り添うことが夫婦関係を長く続けるうえで大切になります。
筆者の経験からのアドバイス
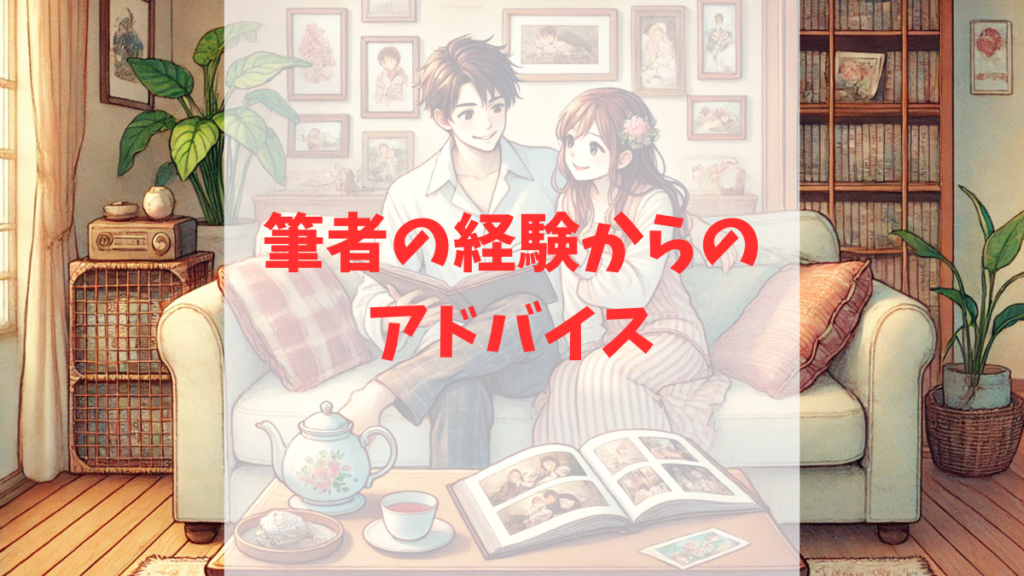
筆者自身、2000年代初頭に中国人の妻と結婚し、上海を拠点に20年近く生活してきました。
結婚当初は親戚づきあいや子育ての考え方の違いに戸惑い、子どもが成長するにつれて教育費や生活費の価値観の違いにも向き合う必要が出てきました。
国際結婚の悩みは、一度で終わるものではなく、家族の成長とともに形を変えてあらわれるものだと実感しています。
そのたびに夫婦で衝突したり、話し合ったりを繰り返してきましたが、今では「どんな家族でいたいか」をパートナーと共有できているという実感があり、穏やかに暮らせています。
国際結婚は、国や文化、価値観が違うからこそ、「同じ未来を見られるかどうか」が何より大切だと感じています。
国際結婚でよかったことは以下の記事で詳しく解説してます。
こちらもCHECK
-

-
国際結婚してよかったこと8選|リアル体験談からわかる幸せのかたち
続きを見る
まとめ|違いはある。でも、それを一緒に乗り越えられるかが大事

国際結婚は、文化、言語、制度、価値観──あらゆる“違い”を日常の中で感じながら生活していくものです。
けれどもそれは、ただ大変なだけではなく、お互いの背景を理解し合い、より深く信頼し合えるチャンスでもあります。
どのテーマも、話し合わずに放っておくと将来的な大きな衝突の火種になりかねません。
でも逆に、今のうちにしっかり共有できれば、ふたりの関係はどんな国境も超える強さを持てるはずです。
もしあなたが今、国際結婚に向けて一歩踏み出そうとしているなら、この記事が少しでも未来を考えるきっかけになれば嬉しいです。

